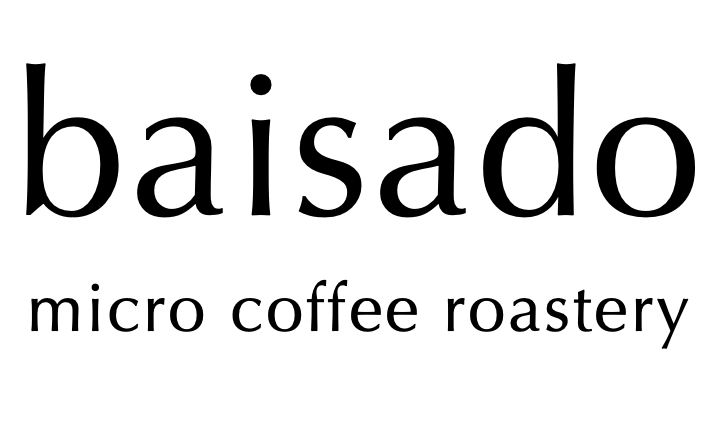早いもので今年も残すところあと半月足らずとなりました。一昨年、昨年に続き、baisadoでの小さな出来事を通じてこの一年を振り返ってみます。
1.ブルーマウンテンコーヒー仕入れ(1月)
新しい年を祝うべく、ジャマイカ産の「ブルーマウンテン No.1」を15kg入り木樽で仕入れました。高価なブルーマウンテンコーヒーは、現地で密封された木樽での仕入れが純正品購入の証明になります。
上品な酸味を活かすため、baisadoの他の銘柄より僅かに浅煎り寄りで仕上げている、混じりけなしの100%ブルーマウンテンコーヒーの風味を、ぜひ一度味わっていただきたいです。
2.アートイベント参加(2-3月)
アートイベント企画ユニット「ねるneru」主催の体験型アートイベント「ぐねる」「トンネル」用にオリジナルブレンドコーヒーをお作りし、期間中に会場でドリンクをご提供しました。来場者の方々にはもちろん、自分たちにとっても大変興味深いイベントでした。
3.スイーツメニュー提供(5月)
厳しい夏の「おしのぎ」として、無糖濃縮コーヒー「コーヒーリキッド」を使った「baisado風アッフォガート」をリリースしました。おかげさまで大変ご好評いただき、秋以降も引き続きご提供しています。暖かい店内で楽しむホットコーヒーとアッフォガート、寒い冬にこそいかがでしょう?
4.「女王陛下」ご訪問(5月)
ある日の夕方、店の外に出て一息ついていると、大きなハチが店に向かって飛んでいくのを目撃しました。どうするのかと見ていると、店の壁に開いた配管用の穴に入っていきます。驚きつつも取り急ぎガムテープで穴を塞ぎ、出入りできないようにしました。
閉店後戸締りしてから片付けをしていると、(たぶんさっきの)ハチが店内に現れて飛び回り、思わず凍り付きました。古い家屋のため室内外に隙間が多く、壁の中を通って出てきたのでしょうか。
ハチを脅かさないよう静かに戸を開けてなんとか店の外に出てもらい、翌朝早速駆除業者に来てもらったところ、おそらくスズメバチの女王で、巣を作る場所を探していたのだろう、ただ幸い壁の中に巣はまだできてなさそうだ、のことでした。
春のスズメバチの女王は巣作りで体力を消耗しているため攻撃性は低いとのことでしたが、もしあのとき気付いていなかったら、今頃店はどうなっていたのでしょう。
5.平日営業開始(7月)
2022年春から3年ほど、基本週末のみの営業を続けてきましたが、今年の7月から平日も営業することにしました。1か月後の感想をこちらに記しています。さらに4か月が経ち、頭も身体もだいぶコーヒー屋仕様になってきた気がします。また、自分たちが当事者になったことで、個人経営の飲食店主をこれまで以上に尊敬するようになりました。続けること自体が目的ではありませんが、自分たちの気が済むまでは続けられるよう、心身の調子を整えていきたいです。
6.フード提供(10月)
baisadoの近隣にはおいしいお食事処がたくさんあるので、食べ物の提供は当初考えていなかったのですが、「虫養い」程度の軽食をご用意してみようと、まずは週末限定で、ご近所のおいしいパン屋「Solo」さんのライ麦パンで作ったサンドイッチをお出ししています。来年は平日にも何かご提供できるよう考えています。
7.麻袋での生豆仕入(10月)
コーヒーの生豆は、本来数十キロサイズの麻袋で流通していますが、高温多湿な京都の夏で劣化するのを恐れ、baisadoでは卸売業者に小分けしてもらってから仕入れています。
ただいくつかの銘柄については販売ペースが上がってきたので、寒くなる秋冬シーズンを待って麻袋で仕入れてみました。重たい麻袋を店頭で受け取り次第、すぐに店内で小分けして密封保管しています。輸入業者の倉庫からの直送となるため卸売業者のチェックが入らず、焙煎前後の検品はよりシビアになりますが、一つ身分が上がった気がして嬉しいです。
8.コラボ商品販売(10-11月)
昨年に続いてご縁をいただき、鹿児島県日置市の美山地区で開催された「美山CRAFTWEEK2025」にて、baisadoのドリップバッグを販売することができました。今年は同じブースに出展される方々とのコラボ商品もご用意したところ、多くの方にお買い求めいただけました。来年もご縁があればぜひ参加したいです。
9.下鴨音楽祭参加(11月)
下鴨エリアの楽器店・飲食店などが共同で開催する「第6回下鴨音楽祭」に参加し、演奏会場を提供しました。前日の営業終了後に焙煎機やテーブルを片付けて平土間にし、椅子やベンチをありったけ並べて十数名ほどお座りいただけるようにしました。当日はあいにくの雨模様でしたが、予想以上に多くの方がお立ち寄りくださり、アンプを通さないアコースティック楽器の生演奏を至近距離でお楽しみいただくことができました。来年も参加するつもりです。
10.賃貸契約更新(12月)
素敵な内部空間に一目惚れして2021年末に店を借りましたが、このたび2度目の更新契約を結ぶことができました。これであと二年は同じ場所で営業を続けることができます。2026年も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。皆さまどうぞよいお年をお迎えください。