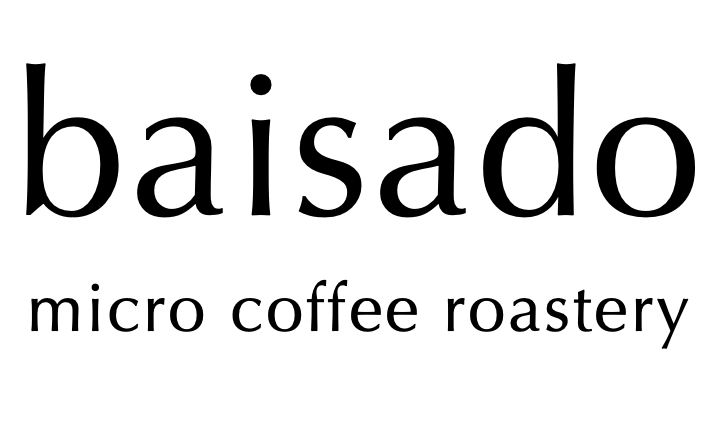前回ご紹介したハワイ コナ産コーヒーにちなみ、今回はこの本をご紹介します。
山岸秀彰「美味しいコーヒーを飲むために-栽培編-」(いなほ書房)
著者はニューヨークで活躍した投資銀行マンで、44歳にしてアーリーリタイア。美しい夕焼けを求めて夫婦でハワイ島・コナ地区に移住しましたが、家の敷地に植っていたコーヒーの木に興味を持ち、経験ゼロからコーヒー栽培を始めた方です。持ち前の探究心と勤勉さで、抜きん出て高品質なコナコーヒーを生産しましたが、重労働のため体を壊し、残念ながら2020年に販売を休止されました。この本では、著者自身が実体験から獲得した、美味しいコーヒー豆作りの持論が展開されます。
著者は、美味しいコーヒー(クリーンでフルーティで甘くて、何時間かけて飲んでも飲み疲れない)を実現できるコーヒー豆を、以下のように定義しています。少し長いですが、引用します。
一本のコーヒーの木から実を摘む際に、水分不足でスカスカの実、カラカラに乾いた実、栄養不足で黄色く変色した実、実の付け過ぎで突然死した実、菌類の影響で茶色に変色した実、高温で疲弊した実、直射日光に焼けた実、窒素焼けの実、虫食いの実、過熟の実、腐った実、カビの生えた実など、あるいは誤って摘んでしまった未熟の実などの欠陥実は別の袋に分別しながら、完熟した実のみを収穫用バスケットに入れ、摘み終わった木には、これから熟す緑の実だけが残り、そこには完熟みや欠陥実は一つも残さず、かつ、地面に実を落とすことなく摘んだコーヒー
「熟した実と欠陥実は全て摘み取り、そこから欠陥実を全て取り除き、逆にこれから熟す実は一つも摘まない」という、言葉にすれば分かりやすいことですが、これを実行すること、他人に実行させることがいかに難しいかを、著者は繰り返し語ります。そしてそれは、実を摘み取るピッカーに対する報酬の極端な低さに起因することを指摘します。これを改善するには、消費者が真に美味しいコーヒーを知り、安くても美味しくないコーヒーを避けることで、生産者がピッカーに十分な報酬を支払うよう仕向けなければならない、そうしなければ遠くない時期に美味しいコーヒーは飲めなくなる、と著者は警告します。
健康に育った木に実った、健康に完熟した実を、ピッカーが丁寧に摘むことこそが、美味しいコーヒー豆づくりの秘訣だという著者の主張は、言われてみれば当然で、しかしはっきりとは気付いていませんでした。生豆を焙煎して販売する私たちには、生産者やピッカーにまで想いを致していそうな取引先から生豆を仕入れることしかできませんので、これまで以上に仕入れに対して注意深くなろうと思います。
内容はシリアスですが、文章は非常に洒脱で、時に笑わされつつスラスラと読めてしまいます。コーヒー生産の実態について興味がおありの方は、ぜひ一度お読みになってください。