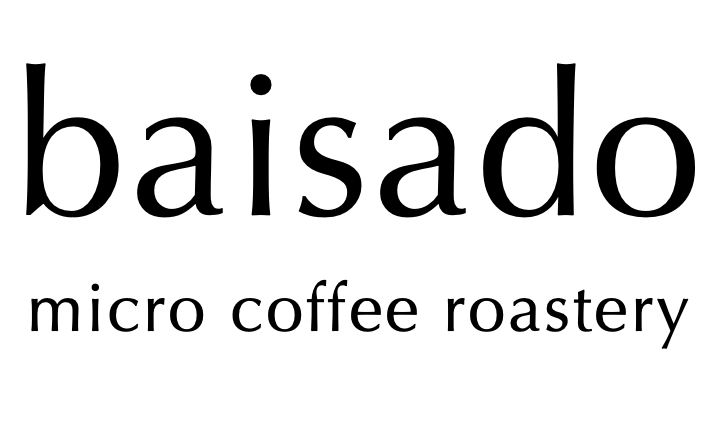秋のお彼岸が過ぎ、猛烈に暑かった夏もようやく終わりが見えてきました。
朝晩の涼しい空気に触れると、ホットコーヒーが恋しくなってきます。
そんな季節の変わり目に、新しい生豆を2種類迎え入れました。
今日はその一つをご紹介します。
コロンビア マグダレーナ “パシオン デ ラ シエラ” ティピカ EX
https://baisado.theshop.jp/items/78704827
ブルボンと並ぶ、最も古い栽培品種であるティピカ100%のコロンビアコーヒーです。
原種の特徴をよく留めているティピカは、樹高が高くて収穫しづらいうえに収量が少なく、加えて病気にも弱いため、生産者が減少しているそうですが、風味は改良品種に勝ると言われています。
この豆の等級はEX(エクセルソ)で、これまで扱っていた商品のSUP(スプレモ)より少し小ぶりですが、焼き上がりはとても美しく、花を思わせる素晴らしい香りがします。
また風味は非常にクリーンで、穏やかな酸味がスッと消えた後に甘みが残ります。冷めると風味がさらに強く感じられ、飲み終えるのが惜しいと思うほどです。
9月からご提供している「秋ブレンド」にも脇役として参加し、風味をグレードアップしてくれている、スペイン語で「山脈の情熱」と名付けられた秋の新商品を、どうぞご贔屓に。